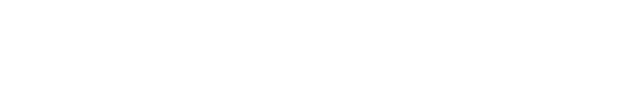部門紹介
診療部
各診療科のご案内
◆内科
〇 糖尿病、高脂血症、高尿酸血症(痛風)、肥満などの生活習慣病、その他内科全般の診断・治療をします。
【担当医師名】
深瀬 裕 医師(常勤)
獨協医科大学卒
「主に病棟を担当しております。宜しくお願い致します。」
外来日:木曜日 午前・午後 第2・4金曜日 午前 第1・3金曜日 午後
仁多 健剛 医師(常勤)
東京大学卒
「緑に囲まれた、清潔で広々とした病院です。体にも心にもよい療養環境が整っています。」
外来日:月曜日 午後 土曜日 午前・午後
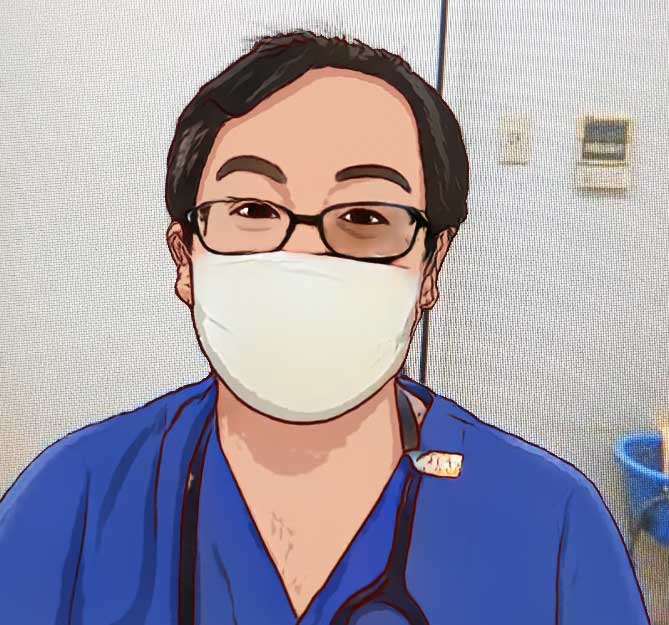 田中 道人 医師(非常勤)
田中 道人 医師(非常勤)
獨協医科大学卒
「糖尿病外来を専門としています。」
外来日:水曜日 午後
◆リウマチ・膠原病
〇 全身の関節や筋肉などに痛みやこわばりを来すリウマチ性疾患の診断・治療をします。
〇 リウマチ性疾患には幅広い疾患が含まれますが、その中でも特に関節リウマチ、免疫異常・炎症制御異常を伴ったリウマチ性疾患等の膠原病の診断・治療をします。
【担当医氏名】
西川 恵 医師(非常勤)
東京女子医科大学卒
「丁寧な診療を心がけています。」
外来日:第2月曜日 午前・午後
◆外科
〇 消化器疾患を中心に幅広く一般外科診療を行っています。
〇 消化器疾患に対しては、胃・大腸の電子スコープによる検査・治療を実施しています。
〇 野田市の胃がん検診
【担当医氏名】
平安 良博 医師(非常勤)
獨協医科大学卒 獨協医科大学外科入局
「消化器外科が専門ですが、関連した内科疾患も診ております。」
外来日:水曜日(第3除く) ・第1・3土曜日 午前・午後
寺内 剛 医師(院長)
川崎医科大学卒 獨協医科大学外科入局
「外科一般を診させて頂いております。ご自身の症状で、不安などがございましたらお問合せ下さい。」
外来日:火曜日・第2・4土曜日 午前・午後
◆ペイン(痛み)外来
〇 病名がわかっているのに長く続く痛みやしびれ、または、原因がわからない痛みや神経の失調等の症状の総合的な診断・治療をします。
〇 頭痛、肩こり、五十肩、膝痛、腰痛、坐骨神経痛、顔面神経麻庫、帯状庖疹、三叉神経痛等の病気の診察・治療をします。
【担当医氏名】
阿久根 透 医師 (副院長)
鹿児島大学卒 東京大学麻酔科入局
「ペインクリニック外来をしています。帯状疱疹などの神経痛で困っている方は、是非ともご相談下さい。内科診療にも対応します。」
外来日:月曜日・火曜日 午前・午後
◆整形外科
〇 骨折などの外傷性疾患を中心に、四肢関節・脊椎・高齢化に伴う大腿骨近位部骨折など整形外科全般にわたる疾患の診察・治療に当たっています。
〇 必要に応じて手術が可能な連携病院、当院のペイン(痛み)外来へ紹介します。
【担当医氏名】
宮入 太朗 医師(非常勤)
山梨医科大学卒
「整形外科外来で整形外科外来全般を診療しております。」
外来日:木曜日・金曜日 午前・午後
◆泌尿器科
〇 一般泌尿器科疾患に対応した診断・治療をします。
【担当医氏名】
小山 雄三 医師(非常勤)
慶応義塾大学卒
「やさしい診療をしております。排尿トラブルの方はぜひ!」
外来日:第2・4土曜日 午前
◆皮膚科
〇 幅広く様々な皮膚疾患(アトピー性皮膚炎、蕁麻疹など)、スキントラブルに対応した診断・治療をします。
〇 必要に応じて当院のペイン(痛み)外来へ紹介します。
【担当医氏名】
松坂 美貴 医師(非常勤)
三重大学卒
「皮膚の事でお困りの際は、ぜひいらして下さい。」
外来日:木曜日 午前・午後
※受診や患者様をご紹介いただく場合は、診察日が変更となる場合がありますので、事前にお電話にてお問い合わせください。
看護部
リハビリテーション科
薬剤部
薬剤部が目指すもの
当院の薬剤師は、患者様だけでなく他の医療スタッフからも頼りにされる存在として、研鑽を積む ことを忘れず業務に従事しています。「何か知りたいことがあったら薬剤科に」となれるよう情報収集・提供を行っています。
薬剤部が行っている業務・・・薬剤管理業務
当院では、オリジナルの薬剤管理システムにより、患者様個々に調剤された薬剤の 全てを記録(薬歴)し、それをもとに、注射薬・内用薬・外用薬を含めて相互作用・ 重複投与等を確認し、薬剤の有効性・安全性を確保しています。 また、薬剤師が直接、患者様のベッドサイドに訪問し、患者様と接することにより、薬剤が副作用なく効果的に使用されているか確認だけでなく、副作用の予兆を早期発見できる(第一発見者となる)ように努めていま す。 入院患者さんには、自分の状態をお話しできない状態の人もいます。そのような 患者さんこそ、薬剤師が力となれることがあります。ベッドサイドに出かけた薬剤師 だからこそ、お薬の有効性・安全性を確保した薬物療法を目指した行動をとれる存在 として行動できます。 さらに薬剤師は、チーム医療の一員として、各種委員会に参加し、しっかり意見を 述べられる存在にならなければなりません。
薬剤部が行っている業務・・・調剤・製剤業務、注射薬の個別セット、無菌製剤業務

- 調剤・製剤業務
当院では、高齢者の入院患者が多いこともあり、院内調剤のほとんどが、錠剤分包機 に より1包化して患者様個々のお薬カートに1回分ずつセットしています。 セットされたお薬を、服用自伝で看護師が配薬しています。 - 注射薬の個別セット
注射薬は薬剤師が、患者個別にカートにセットし、注射薬の配合変化、内服との重複、等をチェックし、 投与上の注意等を看護部と共有しています。 - 無菌調剤業務(高カロリー輸液)
高カロリー輸液は、無菌室内のクリーンベンチ内で混合する ことで、無菌製剤を提供しています。
薬剤部が行っている業務・・・医薬品情報(DI)業務 、院内説明会

- 医薬品情報(DI)業務
お薬情報誌を作成しています。 - 院内説明会
院内医療スタッフを対象に説明会を実施しています。
薬剤部教育制度
【オンラインによる薬剤勉強会】
【個別研修】
eラーニングで必須科目、個人の希望科目の研修を行います。
例)情報リテラシー(情報を適切に判断し、情報を通じて決定を下す能力を学ぶ)
感染対策 (新型コロナウィルスと感染対策)
医療安全 (医療安全の基本、暴力・ハラスメント対策、コロナ対策)
医療機器 (医療機器の基礎知識)
特別企画 (ストレスから自分を護る)
接遇 (接遇とは)
社会人基礎力(医療従事者のためのアンガーマネジメント)
看護補助者( 補助者の役割業務)
【集合研修】
AEDの使い方、BLS研修、医療安全、感染対策、医療機器の知識、ストレスマネジメント、アンガーマネジメントなど
放射線科
放射線科の役割

一般的なレントゲン撮影(一般撮影)だけでなく、CT(コンピュータ断層撮影装置)やMRI(磁気共鳴 断層撮影)を駆使して、より細部にわたる検査を行うことで、患者様の異常を早期に発見することに つながり、また医師の的確な診断を助けています。
一般撮影
- 単純撮影 ・・・ 胸・腹・骨 等の撮影を行います
- 透視撮影 ・・・ 造影剤を使って胃・腸 等の撮影を行います
- 移動型X線撮影 ・・・ 移動が困難な患者様を病棟で撮影を行います
- 骨塩定量測定 ・・・ 骨密度を微量のX線を利用して測定する検査です
CT(コンピュータ断層撮影装置)検査
16列CT装置 『Revolution ACT』を2024年3月より設置しました。 今までのCTより、短時間で高画質な精密検査が可能になりました。CT検査では、X線を使って身体の内部を輪切りにした画像を構成します。頭部や胸部、腹部内の臓器、大動脈、心臓、四肢などの病変に対して様々な画像を得ることができます。また、造影剤を使用することで血管や臓器などの体内の様子をより詳しく描出することが可能です。必要に応じて、撮影した画像をもとに3D画像を作成することもできます。
MRI(磁気共鳴断層撮影装置)検査
2023年6月より富士フイルム製0.3Tオープン型MRIを設置しました。開口部が広く、一般的なMRIのような狭い所が苦手な方でも検査を受けられる可能性が拡がります。MRI装置は強力な磁石と電波を使用して、体中に豊富にある水素原子核を共鳴させて画像化します。必要に応じた任意の断面像が 直接得られ、様々な撮像手技を用いることでCT検査とは異なる情報が得られます。 放射線は使用しないため、被ばくの心配はありません。
栄養課
栄養課の給食業務について

当院の栄養部門は、献立作成、発注、調理全般を 外部委託しています。
- 献立作成 献立は8週サイクルを基本に、旬の食材や調理方法を取り入れ、、月2回の行事食を提供しています。
- 治療食 一般職の献立から、個々の病態にあった治療食献立へと展開を行い、行事職もほぼ皆様と同じ 食事を召し上がっていただくよう工夫しています。
- 行事食 現在、月1回のお誕生日メニュー(お弁当形式)、また駅弁シリーズと銘打って日本全国の駅弁を再現し 皆様によろこんで食べていただいています。
栄養ケアマネジメント
管理栄養士による栄養管理では、全患者様の栄養ケアマネジメントを行っています。
- 他職種と協力して、患者様一人ひとりの栄養状態を把握し、栄養計画及び評価を行い、各人にあった適切な 栄養補給を目指していきます。また、体調不良時や食欲低下の方への個別対応も行い、心身の状態に合わ せたきめ細やかな食事提供を心掛けています。
- 入院患者様及び外来患者様対象に栄養相談も受けています。
医療相談課
医療相談課の役割
当院の医療相談課は「地域医療連携」と「医療福祉相談」の機能を 併せ持っています。
地域医療連携
地域医療連携は主に紹介・逆紹介にかかる業務で、主に「当院への入院を希望される場合」と「当院より他院へ紹介する場合」の『窓口』 としての機能です。 療養病床への入院・転院を希望される患者様がいらっしゃいましたら、そのご家族様や、患者様が現在入院中の病院・入所中の施設 スタッフからご相談を承ります。
療養病床への入院相談の流れ
- ご家族様・医療機関や施設スタッフより当院相談員へご相談いただく
- 入院判定に必要な書類を当院へ提出していただく
- 提出していただいた書類により1次判定を行う
- ご家族様にご来院いただき面接を行う
- 最終判定で入院可能となった患者様はベッドの手配ができ次第、お受け入れする
また、他院への転院・外来受診が必要な患者様へは、先方病院との相談・交渉や受診予約の代行など 円滑に話が進むようにお手伝いします。
医療福祉相談
医療福祉相談は入院・外来全ての患者様とその後家族が対象となりえます。 患者様が安心して治療や療養生活を送ることができるように、経済面・社会面・心理面などにおいて、 ご本人やご家族が抱える問題や不安を解消するお手伝いをします。 以上、「連携」「相談」の2つの面から様々なご相談を承りますが、具体的な例としては・・・
- 今、他のところに入院しているが、当院への入院(転院)させたい
- 今、当院に通院中だが、専門の病院を紹介されたので、どうやって受診すれば良いのか教えて欲しい
- 通院しながらの生活や退院した後の生活に不安がある
- 入院費や生活費など、経済面で不安がある
- 介護保険や年金、障害者福祉などの制度や使えるサービスについて知りたい
- 通所や入所など、利用できる施設について教えて欲しい
- とりあえず相談したいことがあるが、どの職種に相談したらいいのか分からない
保険事務課(医療事務)
保険事務課は病院の維持業務と併設老人保健施設の事務業務を統合する課としての名称です。
病院での業務
外来、入院の医療保険に関する請求を取り扱っており、受付、会計、カルテ作成、保険請求等を行うことが主な業務となっております。2年に1度厚生労働省にて診療報酬の改定が行われるため、改定内容を院内へ発信することも大切な業務となります。
また、来院される方を一番最初にお迎えする窓口ですので、笑顔で丁寧な対応を心がけております。
診療費に関するご相談やその他のご質問等がございましたらお気軽に窓口にお声がけください。
老健での業務
保険事務課教育制度
【診療報酬改定】
診療報酬改定セミナー等に参加し、院内に改定内容を発信
【個別研修】
eラーニングで必須科目、個人の希望科目の研修を行います。
例)情報リテラシー(情報を適切に判断し、情報を通じて決定を下す能力を学ぶ)
感染対策 (新型コロナウィルスと感染対策)
医療安全 (医療安全の基本、暴力・ハラスメント対策、コロナ対策)
医療機器 (医療機器の基礎知識)
特別企画 (ストレスから自分を護る)
接遇 (接遇とは)
社会人基礎力(医療従事者のためのアンガーマネジメント)
看護補助者( 補助者の役割業務)
【集合研修】
接遇研修等